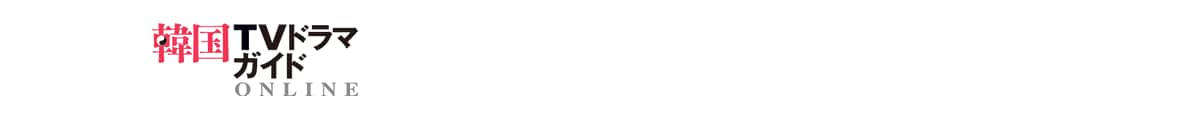■強い国、強い王をめざして戦い続けた武闘派代表格、朝鮮王朝第3代王・太宗
幼い頃から神童と呼ばれ、16歳で科挙に合格したイ・バンウォンは、武人ばかりを輩出していたイ家待望の文官だった。だが、役人となって知ったのは、貴族が腐敗しきった高麗の危機的状況。そのため、国王中心の中央集権体制が必要だと考えるようになり、のちに朝鮮王朝の太祖となる父・イ・ソンゲ(李成桂)、そのブレーンであるチョン・ドジョン(鄭道伝)らと革命を決行する。
父のため、新しい国のために、誰よりも体を張った(開国反対派のトップのチョン・モンジュ〔鄭夢周〕の暗殺までも担う)バンウォン。にもかかわらず、王の後継者候補はおろか開国の功臣記録からも除外され、父やチョン・ドジョンへの不満を募らせていく。
やがて、太祖が病床に伏せっているときを見計らい、腹違いの弟である世子バンソク(イ・ソンゲ八男/芳碩)、宰相政治を目指すチョン・ドジョン一派を一掃(1398年・第一次王子の乱)。その後、実兄・バンカン(イ・ソンゲ四男/芳幹)による第二次王子の乱を鎮圧した1400年。兄・2代定宗(チョンジョン:イ・バンクァ/李芳果)の譲位によって、3代王に即位する。
王となったバンウォンはそれまで進めてきた王権強化を固めていく。
私兵を解体し新王朝を脅かす武装勢力を排除。軍事制度を整備し、国防を強化した。高麗時代に得た土地や奴隷を抱える仏教界を弾圧し、土地を回収、奴婢を官庁の所属にし、国庫の財源確保にも動いた。役人の登用には実力主義を取り入れ、科挙制度を充実させるなど、教育や外交にも精力的に取り組んでいる。また、庶民が王に直訴できる「申聞鼓(シンムンゴ)」で、無実の人民が自由に請願できるようにするなど、新しい社会政策で民心を得ている。
一方でよく知られているのは、王権を脅かすもの、その危険因子の徹底排除だ。外戚であろうが、功臣であろうが、容赦無く粛清していく。革命、王位簒奪、外戚排除……と、三男で、朝鮮独自の暦やハングル制定などで知られる聖君、4代王・世宗(セジョン)へのへの譲位後まで続く一貫した刀(武力と権力)での支配は残虐非道、やりすぎ感が否めない。だが、まだなにもかもがあやふやな新王朝において、国を安定させるためには圧倒的な力は必要だったのもまた事実。必要悪、時代が生んだ悪役ともいえるだろう。
そう思うと、捨てられた怒りを糧に野心を燃やしたものの、玉座を手に入れたと同時に、失ったものの大きさに愕然とする、『私の国』のバンウォンのなんともいえない寂しさ、空虚に満ちた表情が頭から離れない。そういえば、『六龍が飛ぶ』のユ・アインも、何かを決断するたびに志をともにした仲間を手放し、孤独を深めていったっけ……。
王とは孤独なもの。人は彼を「血の王」と呼ぶけれど、もしかすると、「血の涙の王」なのかもしれない。