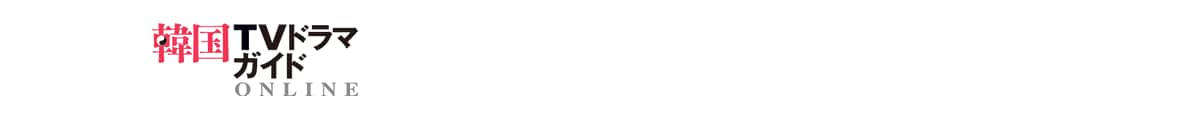ウィ・ハジュン 重点を置いた部分は……。今日の現場のキッチンカーは何かな? 今日のメニューは何かな? あはは。僕の場合は、現場の「楽しさ」だったと思います。もちろん、演技は重要です。作品に臨むときは常に最善を尽くして演じますが、僕は何よりも、現場自体が、毎日が楽しいことが重要なんです。なぜなら、この作品は、とても荒々しくて、肉体的にもきつくて、感情的にもプレッシャーが多いシーンが続くので、本番は皆とても大変だったんです。けれど、カメラが回っていないところでは、こんなにも楽しく撮影ってできるものなのかな、と誰もが驚くくらい、大変さより「楽しさ」が勝る現場でした。こんな大きな幸せを感じたのは初めてです。僕も、「明日はどんな話をしようか」「明日はどうやって笑わせようか」と、ずっと考えていていました(笑)。
チ・チャンウク ハジュンは、毎日「どうやって笑わせようか」と意気揚々と現場にやってきたんです(笑)。それで、撮影がすべて終わった打ち上げのとき、泣いたんですよ。すごく感動して、この現場がもう終わるのが寂しくて残念で……って言って泣いたんです。あげく、笑わせるネタがなくなって、泣いてみようかと思ったと……(笑)。泣きながら笑わせていましたね。
ウィ・ハジュン はい、その通りです(笑)。
イム・セミ (2人のやり取りに笑いながら)今二人がお話したこと、すべて大事だと思います。私自身は、一緒に話をしながら作っていく過程を大事にしました。撮影現場に行くと、まず「私はこういう考えでこう表現しようと思う」という話をお互いにして、なによりも会話を重要視していました。それに、私が演じたウィジョンは、少し混乱するような状況に置かれ続けるんですが、台本を何度読んでも、あまりに複雑で難しい状況で、この感情をどう整理すればいいかわからなかったんです。それで、監督や二人にも、これはどう思う?と聞いて助言を求めたりしました。そんなふうに初めは感情の整理をしなければと悩みましたが、やればやるほど整理がつかないことが多すぎるんです。それで、整理しないのが答えなのかもしれない、答えを出すのではなく、そのまま演じることが大事なのだと思うようになりました。それで、状況や感情が混乱したまま整理しないでおくことに務めました。

――役作りのためにどんな準備をしましたか?
イム・セミ 今話したことと少し似ていますが、感情や状況の整理についてまず考えました。それと、舞台設定が1990年代だったので、その時代の人々はどんなマインドで仕事をしていたのかも考えました。90年代のドキュメンタリーを観たり、事件を探したりもしましたし、女性で仕事を持っていた人たちはどのように過ごしていたのか、両親に聞いたりもしました。現場にいらっしゃる方々、スタッフの方々と会話もたくさんして、その時代に生きてきた人たちの気持ちをどう表現するか、たくさん悩みましたね。また、見た目についても本当にたくさん相談しました。衣装もたくさん着て、この時代にこれは合っているかなと確認しながら決めていきました。
ウィ・ハジュン (自分が答える番になって)ええと……。
イム・セミ (ハジュンの方を向いて)何をどう準備しましたか?
ウィ・ハジュン 明日はどうやって笑わせるか(笑)。
――(笑)役割についてで……。
(三人で大爆笑)
ウィ・ハジュン 見た目の部分では、当たり前ですが監督と衣装チーム、メイクチームとコミュニケーションをとりながら作っていきました。何よりも神経を使ったのは、チョン・ギチョルというキャラクターの眼差しですね。とても冷たく、とても冷徹で、「いったいあいつは何を考えているのか」そう思われるような眼の光、表情について、意識して演じていたように思います。そんなギチョルがウィジョンに会ったときは口調や眼差しがどう変わるのか、ジュンモと二人でいるとき、少しずつジュンモを信じていく過程で見せる眼の光の変化、そんな部分に一番重点を置いて、研究しました。

チ・チャンウク 僕は撮影に入るずっと前に台本を受け取り、監督と脚本家さんとミーティングをし、台本を修正しながら準備をしていました。
――どれくらい前から?
チ・チャンウク 撮影の6カ月前に初めて台本をもらって読みました。その後、監督や脚本家さんとミーティングをし、その後も監督と、台本にあるセリフ、人物像について何度も話し合って、悩みながら詰めていきました。特にジュンモという人物像については、監督とのコミュニケーションを通じて、お互いの考えをすり合わせていった感じですね。それと、僕が一番重点的に準備し、気を遣ったのは、『最悪の悪』チームの皆との連帯感です。連帯感を積むためにベストを尽くしました。そのうえで、人物、現場、置かれた状況に、自分が刺激を受けられるような状態を作る努力をたくさんしました。このドラマだけでなく、毎回作品に臨むときには似た過程を経ます。パク・ジュンモというキャラクターのために身体作りをしたり、アクションを習得したり、そういった特別な準備はなかったと思います。むしろ、現場で緊張感を維持するために監督とのコミュニケーションをたくさんとりましたね。