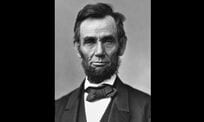■実は賄賂常習者だった?
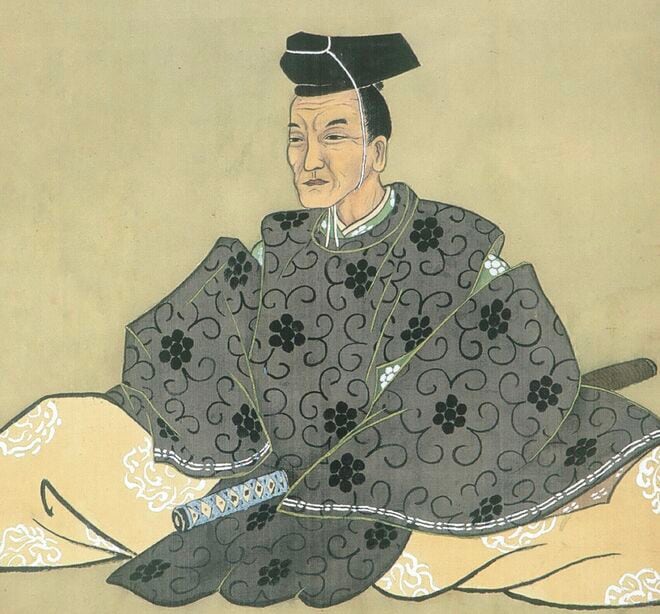
定信に刺し殺されるところだった(!?)田沼意次。しかし、その関係は実は……
画像:Public Domain via Wikimedia Commons
田沼意次といえば賄賂。大名や役人から次々に賄賂を貰う田沼を定信は嫌いに嫌い、「刺し殺してやろうと思った」と家臣に愚痴ったこともあるらしい。それほど田沼を否定したのだから、定信は決して賄賂をしなかった――わけでもない。
1783(天明3)年12月18日、定信は従四位下の官位を得ている。実はこのとき、定信は朝廷や幕府の各所に賄賂を贈っている。しかも、その際に家臣に漏らした“言い訳”が振るっている。
「私は賄賂が嫌いだ。しかし、今の風潮で行なわないのは逆に愚かだ。出世は誰でもしたいのだから、悪いのは受け取る側。自分が贈ったのは、御家のためだから正当だ」
つまり、賄賂は受け取りを拒否しなかった側が悪いので、藩のために贈る自分に罪はないと強弁したのだ。
■目的のためには宿敵にも賄賂!?

田沼を斬ろうとした定信は主君の11代将軍・徳川家斉に斬られそうになったことも。
画像:Public Domain via Wikimedia Commons
さらに、1786(天明6)年にも有力幕臣に贈賄を贈っている。家臣の駒井忠兵衛が記した『鶯宿雑記(おうしゅくざっき)』によると、この年に定信は梅を活けた銀製の花活をその幕臣に送った。「梅の花=梅鉢家紋の松平家」を厚遇するよう求めたそうだ。
その有力幕臣が、なんと彼の宿敵・田沼意次である。
ただ、「定信も賄賂が好きで、意次とも実は仲良しだった」というわけではなく、田沼政治と賄賂の全盛期だから、藩を守るために仕方なかったというのが本当のところだろう。なお、定信自身は賄賂を受け取ることは一切なかった。
■改革は田沼政治のパクリだった?

だいぶお歳を召してからの松平定信の肖像。穏やかな表情になった?
画像:狩野養信筆, Public domain, via Wikimedia Commons
定信の政策の柱は、田沼時代の否定だったとされてきた。その最たる例が、農業主体への回帰と質素倹約を中心とした寛政の改革だった。ところが、商業政策は田沼時代の要素をけっこう受け継いでいる。
たとえば株仲間。意次は商工業の組合である株仲間から上納金を得ていたが、定信もその方針を受け継いでいた。解散させられたのは目立ち過ぎた一部だけ。やはり上納金のうまみは、定信も無視できなかったらしい。
さらに、経済顧問の勘定所御用達には豪商を採用し、商業向けの公金貸付は続けるなど、商人との関係も大事にした。その結果、商業界と幕府の結びつきは、定信時代も続くことになる。
倹約令も、田沼時代の末期から始まっていたのを受け継いだに過ぎない。寛政の改革から、新たにスタートしたわけではないのだ。しかも、倹約のやりすぎは「天下の衰微(衰退)」になるからダメとも考えていた。
つまり、寛政の改革は意外と意次の政策を参考にしていた。意次の人間性を嫌ってはいたものの、政治の才能は認めざるを得ない。そして、目的の為なら意に沿わぬ手段も実行する。
松平定信という人物は、政治に関して究極の現実主義者(リアリスト)だったようだ。
『江戸のワイロ もらい上手・渡し上手の知恵くらべ』童門冬二(文春ネスコ)
『松平定信 人物叢書新装版』高澤憲治(吉川弘文館)
『松平定信 政治改革に挑んだ老中』藤田覚(中公新書)
『歴史文化ライブラリー456 江戸の出版規制 弾圧に翻弄された戯作家たち』佐藤至子(吉川弘文館)