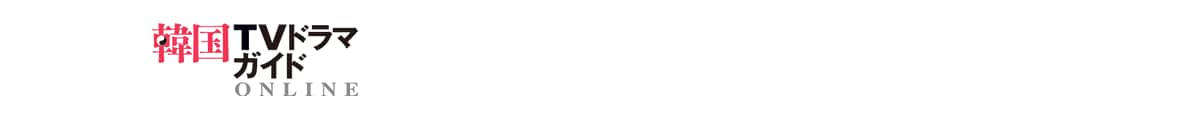■明るい兆し
この時代、我が国で明るい兆しを見出すのは容易ではなかった。
強いて挙げるなら、96年にワールドカップの韓日共催(2022)が決まったことだ。ただ、すべての面で日本に後れをとっていたような我が国だが、サッカーだけは勝っているという意識が強かったので共催の受け止め方は正直微妙だった。
もうひとつは98年の金大中政権の誕生だ。71年の大統領選挙で朴正煕に惜敗。73年には東京でKCIAに拉致され、80年には全斗煥に内乱罪を捏造され死刑判決を受けアメリカに亡命。その後、2度の落選を経て、ようやく大統領になった。金大中は反軍事独裁の象徴的存在だったので、我が国が根本的に変わるような期待が生まれた。
そして、個人的に注目していたのは98年に公開された韓国映画だ。当初は我が国より日本で評価されたように見えた『八月のクリスマス』(ハン・ソッキュ、シム・ウナ主演)は、私の周囲の日本人のあいだではいまだに話題に上る。『情事 an affair』(イ・ミスク、イ・ジョンジェ主演)は当時の我が国では珍しい抑制のきいた表現方法が印象的だった。不良系青春映画の金字塔『太陽はない』は20代のイ・ジョンジェとチョン・ウソンが眩しかった。ホン・サンス監督の2作目で、24年後に日本で正式公開された『カンウォンドのチカラ』は最初、何を見せられているかよくわからなかったが、中毒性があり、いまだにDVDを観ている。この年はその数年後に脚光を浴びる監督や俳優の作品、あるいはエポックメイキングな作品が多かったのだ。
当時、ソウルまで来てこれらの作品を観ていた日本の知人が何人かいた。彼らが熱く語る様子を見て、我が国の映画も国際的に評価される可能性があるのかもしれないなと思った記憶がある。それから約20年を要したが、『パラサイト 半地下の家族』が米国アカデミー賞を獲ったときはじつに感慨深かった。


90年代後半はスマホもSNSもなかったが、韓国の情報に飢えていた一部の日本人はわざわざ麻布や日暮里の韓国スーパーに行ってドラマや映画のビデオを借りていた。たとえ渡航できなくてもワンクリックで何もかも手に入る今とは大違いだが、一人ひとりの熱量は今とは比べられないほど大きかった気がする。
『二十五、二十一』の登場人物、なかでもキム・テリ演じるドヒはそんな90年代の人々を思い出させてくれる、かしましいキャラクターだ。青春ドラマでありながら、50~60代のファンが多いのはそのせいだろう。