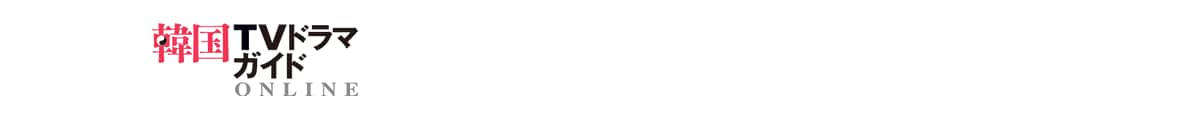ソウルにいると、なぜかウズベキスタン料理を食べたくなる。毎日の韓国料理から少し目先を変えたいから? 韓国語ではない世界に入りたいから? ウズベキスタンのパンや羊肉のケバブを食べたいから?
すべて違う気がする。
日本でもたまにウズベキスタン料理の店に行く。といってもいつもテイクアウト。それもノンと呼ばれるパンをひとつ……。その店は中野駅と西武線の新井薬師駅の中間ぐらいにある。僕はたまに、その店の脇を自転車で通る。時間帯にもよるが、夕方、そこを通り、店が開いていると、ついノンを買ってしまう。小麦粉の値あがりが影響しているのか、以前に比べればサイズは小さくなったが、味は変わらない。
好みはあるだろうが、パンのなかで、僕は中央アジアのパンがいちばんしっくりくる。パンを食べているという充実感が伝わってくる。中央アジアのパンは欧米や日本のそれほど発酵を進めないで焼く。香ばしさと同時に、主食としての存在感が伝わってくる。
もちろん、ソウルのウズベキスタン料理店には、そのパンはある。しかしそれが足を向ける要因ではない。
■ソウル東大門近くにあるウズベキスタン料理店
ソウルのウズベキスタン料理店からは家族とか一族といったものが伝わってくるのだ。韓国の飲食店のレベルは高い。しかしそこから一族……という空気は伝わってこない。日本のウズベキスタン料理店もそうだ。なぜだろうか……といつも思う。
ソウルのウズベキスタン料理店は数軒が、東大門歴史文化公園駅の近くに肩を寄せあうようにつづいている。曲がりくねった路地を入ったところにある。僕は店の名前を覚えていない。店を正確に覚えているわけでもない。おそらくその数軒のすべてに入って、ウズベキスタン料理を食べている。どこもはずれがないというか、同じ人がつくっている気がする。それほど味が似ている。
どこかの店が中心なのかもしれない。そこで料理の素をつくり、各店ではそれを焼いたり、サブジというにんじんサラダはそれを盛りつけたり……つまりこの数軒は、どこかの店がセントラルキッチンのような役割を果たしていて、その周りに増殖する細胞のように広がっている気がする。そうでなければ、あの安定した味は出せないと思うのだ。
そしてその数軒を営んでいるのが、皆、血がつながった一族なのだ。僕はウズベキスタンの言葉も、韓国語も話せないから、互いのあやふやな英語のやりとりなのだが、店の経営者の話をすると、「隣の店は弟」、「路地の入口にある店はおじさん」。……そんな会話が返ってくる。
以前、この店によく行っていた頃、客の大半はウズベキスタン人など中央アジアの人たちだった。仕事は……おそらく東大門市場での衣料品の買い付けだった。市場で売れ筋の衣類を大量に買い、ウズベキスタンなどに運んで現地で売りさばく。運び屋に毛が生えた仕事のようにも映るが、規模が小さな貿易商といってあげたほうがいいのかもしれない。